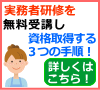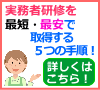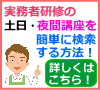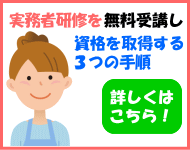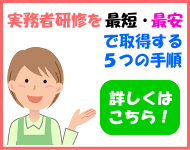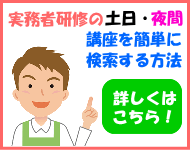介護職の勤務シフトと1週間の勤務時間、夜勤や休暇の実状・実態について紹介しています。
介護は人と24時間関わり利用者の生活を支える仕事
何日くらい、どのくらいの時間働くかということは、就職し仕事をする際の最も重要な労働条件になりますが、介護職の仕事については、職員全員が一斉に8時半に出勤し17時半に退勤するということは現実的には難しい職種です。
介護を受ける方は生身の人間ですから早朝や深夜でも、24時間時間帯に関係なく介護を必要としている方が沢山います。
しかし、介護職員も人間ですから、休み無しでは疲れが溜まり用事も済ますことができず健全な生活を送ることはできません。
では介護福祉士など介護職員の勤務実態は、実際どのようになっているのでしょうか。
介護が常時必要な高齢者が入居している特別養護老人ホームなどでは、勤務時間帯を4パターン程度に区切りシフトを組んで介護を行っているところがほとんどです。
具体例を挙げると、介護スタッフ数人で次のような時間帯でシフトを組み交代で介護を行います。
- 日勤:
8時30分に出勤し、17時に仕事が終了する。 - 早出:
勤務時間は日勤と同じで、出勤時刻が日勤の前に設定されている。 - 遅出:
勤務時間は日勤と同じで、出勤時刻が日勤の後に設定されている。 - 夜勤:
夕方に出勤し、翌朝まで勤務する。
日勤と早出・遅出は勤務時間が少し重なっていますが、これは早朝や夕方の介助に人手が多く必要になるのと、引継ぎなどを行うためです。
介護スタッフの昼の休憩については、交代制で休むことがほとんでです。
また、日勤の時間帯は食事・入浴・レクリエーションなどを行うので、介助スタッフが多く必要になりますが、夜勤は利用者が睡眠を取るので、介護スタッフは数人で対応します。
夜勤の場合は長時間勤務になるので、勤務時間途中で数時間の仮眠を設定している施設もありますが、利用者の呼び出し回数が多い時や、緊急時には仮眠をとる暇がないという場合も少なくありません。
上記以外に当直という勤務形態もあり、夜間に施設内の見回りを行う必要がありますが、それ以外は当直室で寝ることもでき、何か緊急事態が発生した場合にのみ対応すればOKです。
当直勤務は、重度要介護者がいない介護施設では夜勤ではなく当直で対応する場合があり、夜勤の介護スタッフが少ない施設では、夜勤業務をカバーするために当直スタッフを雇っている場合があります。
介護職の夜勤の実態
介護福祉士の有資格者で夜勤をしている方は全体の30%程度で、月の夜勤回数は、4回が約40%、5回が約20%、3回が約15%となっています。
24時間介護の特別養護老人ホームで働く場合は、月に4~5回という施設が多いですが、デイサービスセンターなどでは、日勤時間帯の介護が主なので夜勤は一般的にありません。
しかし、複合介護サービスを行っている介護施設の場合は、夜勤が特定のスタッフに集中しないよう負荷を軽減するために、デイサービスで働いている介護スタッフであっても入居介護施設などで月に1回は夜勤を行うように勤務形態を定めている施設もあります。
訪問介護の勤務期間には、次の2つのパターンがあります。
- 一般訪問介護:
朝から夕方までの日勤時間帯にサービス提供する訪問介護で、通常は夜勤はありません。 - 夜間対応型訪問介護:
夜間における利用者からの要請や定期巡回に対応した訪問介護で、昼間より夜間勤務が主になります。
以上のように介護職の場合は一般企業よりも変則的な勤務が多くなりますが、決まった起床時間に起きるようにするなど生活リズムを一定に保つように工夫するなどすれば、あまり苦にならないという方も結構いるようです。
また、日曜日や夜間に勤務することも多いので、平日や昼間に休みが取れて便利だという方もおられます。
その後、実務経験を積み重ねてある程度の年齢に達した頃には、高度な介護知識や技能が身に付いているため、変則勤務がほとんど無い管理職・相談員・講師などの職種に就けるチャンスがあるのも魅力です。
介護職の1週間の勤務時間
介護職の勤務スケジュールは月単位で決定されますが、これは一般企業の従業員と同じです。
完全週休2日制を導入している特別養護老人ホームの場合は、週に2日は休みになります。
夜勤が月4、5回であれば週1回の夜勤となり、夜勤1回で日勤2日分とカウントできるので、週5日の内、残り3日が日勤で、早出と遅出は1日ずつという勤務形態になると思います。
実際は、各施設のマンパワーや事情や状況により、勤務シフトや時間配分には違いがあります。
一般企業とは違い介護職の勤務時間帯は不規則ですが、正職員であれば日勤で8時間、週5日勤務で合計40時間の労働時間なので、他の業種と同じ労働条件になりますが、日勤であっても残業をしないといけない場合は当然あります。
特別養護老人ホームで働く介護職の1週間の勤務シフト例
- 日:遅出
- 月:夜勤
- 火:夜勤明け
- 水:休み
- 木:休み
- 金:早出
- 土:日勤
介護職の休暇の実態
介護職の有給休暇については、労働基準法の条件を満たしている従業員は、勤務年数に応じ取得できると定められていますが、介護現場においては急病など以外で突然休むのはあまり感心できることではありません。
介護職でも有給休暇は当然の権利ですが、勤務シフトを組んで交代制勤務で対応している場合は、自分が休みたいからといって急に休むわけにはいかないのが実態です。
予期せぬ事故やインフルエンザにかかってしまった場合などは仕方ありませんが、ゴールデンウイーク、年末年始、盆休みなど決まっている休日以外で休みたい場合は事前に希望日を申告して、同僚スタッフと譲り合い協力して休める日を決定するようにすべきです。
介護の場合は、急に欠勤すると他のスタッフが無理して介護業務を代行することになり、他の介護職員に迷惑をかけることになりますので、日頃から健康管理を怠ないように努力することが大切です。