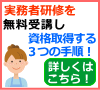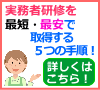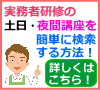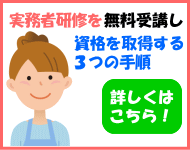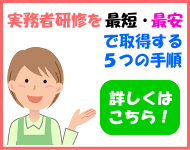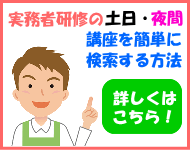実務者研修の医療的ケアで実施される経鼻経管栄養の実技講習に関しての実施内容と手順や注意点について実技演習動画も含めて詳しく解説しています。
目 次
経鼻経管栄養法とは、下図のように鼻から胃までチューブを挿入し、栄養剤などをチューブから注入する方法です。
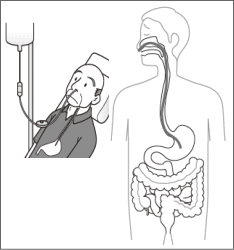
1. 経鼻経管栄養前の確認事項と準備作業
- 医師の指示等の確認
- 利用者の氏名
- 注入する栄養剤の種類
- 注入量
- 注入方法
- 注入時間
- 留意点等
- 手洗い・手指消毒
- 必要物品・器材の用意と確認
- 指示された栄養剤(流動食)の種類・量・投与時間を再確認
- 注入準備を行う
- イルリガートルの内側を触らないようにしてフタを開ける。
- クレンメとチューブ先端の専用キャップが閉じられている事を確認後、栄養剤を入れイルリガートルのフタを閉める。
- イルリガートルを点滴スタンドにS状フックで吊るす。
- 点滴筒をゆっくりと押して点滴筒内に1/3~1/2ほどの栄養剤を満たす。
- チューブ先端の専用キャップをはずし、クレンメを少しずつ開けながら、経管栄養セットの先端まで栄養剤を行き渡らせた後、クレンメを閉じる。
※先端が不潔にならいよう専用キャップをするか清潔なガーゼの上に置く。 - カテーテルチップシリンジに指示され量の白湯を入れ、上に向けて空気を抜き清潔なトレーの上に乗せる。
- 準備した栄養剤などを利用者の元に運ぶ
※栄養剤は腐敗の恐れがあるので作り置きは禁止。
- 利用者本人の確認
- 経管栄養実施に当たっての注意事項などを利用者に説明
- 注入栄養剤が本人のものか再確認し、逆流しないように適切な体位や環境を整備する。
- 経管栄養チューブに破損などがないか確認し、栄養点滴チューブと経鼻経管栄養チューブを接続する。
※チューブがねじれたり折れたりしていないか、またチューブ挿入部の周囲の皮膚の状態も確認。
2. 経鼻経管栄養の注入開始
- クレンメを緩めて栄養剤の注入を開始。
- 滴下速度が、担当医師の指示通りか確認。
- 注入開始直後の利用者の様子を観察し、全身状態に異常がないか確認。
- 注入開始から30分後、注入中の利用者の表情や状態について次の項目を観察。
- 腹痛、吐き気、嘔吐、下痢などが起きていないか。
- 青ざめた顔色をしていたり、唇の色の変色はないか。
- 冷や汗をかいたり、呼吸・脈が乱れていないか。
- 意思伝達ができない利用者の場合、苦しい表情をしていないか。
- 注入後、30分くらいの間隔で定期的に注入中の利用者の体位を観察し、栄養剤が詰まっていないか滴下速度が適当かなどを確認。
3. 経鼻経管栄養の注入終了後
- 栄養剤の注入終了後、栄養点滴チューブのクレンメを閉めて接続を外す。
- カテーテルチップシリンジを使用して経鼻経管栄養チューブに指示された量の白湯を注入し、利用者の状態を観察する。
- 経鼻経管栄養チューブのクレンメを閉め接続を外し、チューブの注入口のストッパーを閉める。
- 注入直後に仰臥位にすると、注入物が逆流するので、栄養剤の注入が終了した後も、30~60分間は半座位の姿勢を保つ。
4. 経鼻経管栄養の報告・片付け・記録
- 手洗いをする
- 実施後の報告
- 観察項目
- ヒヤリハット・アクシデント内容
- 使用物品の後片付け
- 経管栄養注入の状況を記録