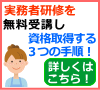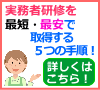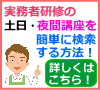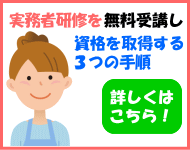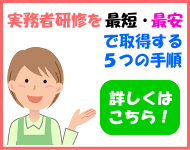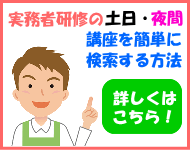介護福祉士は利用者の身体面の介護だけでなく、精神面に関してもサポートすることが求められます。
本来の介護とは、利用者の身体面に対する手助けだけでなく、メンタル面や社会参加など、利用者が生きていく上で障害を取り除けるよう総合的な観点からサポートすることです。
介護福祉士が認識すべき行動指針
介護福祉士は、介護理念を現場で実践に移すためには、下記事項を行動指針として認識しておく必要があります。
- 利用者の尊厳の保つ
- 利用者の自立支援を行う
- 利用者の残存機能を活用する
- ノーマライゼーションの実現を目指す
- QOLの向上を目指す
これらが介護の基本理念であり、知識として知っているだけではなく、現場で実践できる行動力と技量が求められます。
介護福祉士が備えるべき適正
介護福祉士は介護業務を的確・円滑に行うためには、次の適正を備えておくことが大切です。
- 障害・虚弱・高齢にある要介護者の心理状態や気持ちを正しく認識し理解しようとする姿勢。
- 利用者の人生、生活習慣、価値観、人間観などを会話・観察などから読み取る理解力。
- 利用者の意思や考えを尊重する気持ち。
- 利用者の体調や感情、日常生活上の異変について的確に気付ける観察力。
- 利用者の状態や状況に対して最適な支援方法を検討・策定し、提案・助言できるだけの介護専門知識。
- 利用者が納得できる論理的根拠に裏づけされた正確で熟達した介護スキル。
介護福祉士に求められる資質
2000年の介護保険法が施行される直前に有識者や専門家により、今後の介護・福祉専門職の教育課程のあり方が検討されています。
その検討会では下記に示す資質を身につけることが介護福祉士として望ましいという意見が大勢を占め介護福祉士として期待される理想像が示されました。
- 教養を幅広く身に付け、感性や受容性豊かな人間性を養い、コミュニケーションを上手く図り、利用者やその家族との信頼関係を構築すること。
- 利用者の状態や状況を的確に判断し、それに見合った具体的な介護方針を決定して実行し、実施状況をモニタリングして効果検証できること。
- 要介護者の人権や生命を尊重しながら、自立支援に重点を置いた介護を行えること。
- 医療・保健・福祉分野に従事する専門職とも連携・協力して介護を行えること。
- 自分自身の資質や能力を向上させるべく自己研鑽すると同時に後継者の人材育成にも貢献すること。
介護従事者に求められる倫理
介護福祉士をはじめとする介護従事者などが必ず遵守することが求められる介護倫理とは、次のような内容になります。
①信用失墜行為の禁止
金銭面、時間面、約束事などについて、第三者から疑念・不信を持たれるような言動は厳重に慎みこと。
②秘密保持義務
業務上知り得た利用者やその家族に関する個人情報を第三者に他言又は漏洩させてはいけない。
③医療関係者との連携義務
利用者の容態変化にいつでも対応できるよう医療専門職である医師・看護師などと、密に連携しチームケアを行えるような姿勢で臨むこと。
④資格名称の使用制限
現場で介護・相談・援助などの業務に従事する場合、介護福祉士や社会福祉士の資格を持っていない介護職が、その資格名称を所持しているように名乗ったり、記載したりしてはいけない。
ちなみに、日本介護福祉士会の倫理要綱には、次のように記載されているよです。
- 利用者本位・自立支援。
- 質的向上への研鑽・専門的なサービス提供。
- プライバシーの保護。
- 医療・保健・福祉との連携と総合的なサービス提供。
- 利用者の真のニーズを把握と代弁者の役割。
- 地域の福祉推進と住民への関わりと働きかけ。
- 介護を担う後継者人材育成への貢献。
介護従事者に求められる感覚・感性とは
介護職員が現場で介護業務を行う際、どのような感覚が求められるのでしょうか?ここでは必要となる専門性や感性について紹介しています。
介護技術以外に普通の感覚をしっかり持つことも重要
ベテランの介護福祉士などは、介護職員こそ一般常識的な感覚を身に付けておくべきだと力説する人が結構います。
一般常識的な感覚とは何かを考えてみると、保育士などの資格を取得しようと思ったら、音楽や絵などの基礎知識は習得することが必要でしょう。
絵を書いたり図工をしたりピアノを弾いたりできないと保育士や幼稚園などの仕事はできません。
そう考えると介護の仕事はどうでしょうか?
介護では相手は人生経験豊富な高齢者の方が多く、絵画・音楽・習字・お茶・お花・舞踊などプロレベルの趣味を持っている人も多くいます。
一方、介護資格の研修課程には、介護・福祉に関する座学と実習だけで、このような科目はなく資格を取得できます。
しかし、本当に高齢者が満足するよう相手をするには限界があり、これは多くの高齢者の相手をしてきたベテランの介護士になるほど実感するようです。
このサイトを閲覧している皆さんは、介護サービスのプロを目標に資格を取得し、介護現場で経験を重ねて介護福祉士やケアマネジャーの資格を取得しようと目指しているのだと思います。
なので、介護のプロとして利用者の暮らしを良くするためにもっと支援していきたいという熱意を持っていると思います。
ですが、介護のプロであるのと同時に一人の年輩者としての暮らしのサポーターであるという事実もよく認識しておくべきです。
介護だけでなく、高齢である年輩者の人生に一人間として普通に接し、日々の生活に生きがいや希望を持ってもらえるようにするには、利用者の人生観や暮らし方に対しての観察力が必要になります。
介護という観点だけでなく、利用者や家族が必要としていることを、一人間という視点で考え、できることは何かを真剣に考える必要があります。
その結果、普通の感覚で考えれば介護技術に関すること以外に学ぶこともあるはずです。
特に一般常識である挨拶、約束を守る、時間を厳守するなどの感覚をしっかり持つことも大切です。
介護技術以外にも求められる専門性とは
利用者に本当に喜んでもらうには、マッサージやメークを勉強するのも一つの方法です。
実際、介護士の中には仕事をしながらアロマやリフレクソロジーの講座を受講している人もいます。
リフレクソロジーとは、手足をマッサージし心身のストレスや疲れを軽減させる有名な手法です。
ストレス社会という事もあり、癒し系のマサージを行っている店が各地に多くありますが、シルバービジネスの業界でもニーズの高い分野でもあり、年輩者にも人気となっています。
実際、介護サービスの利用者にこれらのマッサージを行うことにより、心と体が癒されリハビリの一種にもなります。
また女性の利用者に対しては、お化粧を施してあげることで、外出もほとんどせず元気がなかった方でも生き生きとしだし、表情も明るくなり認知症の症状も良くなりだした方もおられます。
これは、コスメティックセラピーとも言うようで、本来持っていた社会性や社交性を引き出せた結果かもしれません。
このように、一般社会では普通に習っているようなことが、介護を行う上でも重要な役割を果たす場合もあるので、このような意昧での一般的な感覚も必要になります。
要は介護技術だけに固執せず、様々な方法で利用者の活力を高め生活にも潤いを得られるようなプラスアルファの専門性も必要であるという事です。
介護の職種と資格を生かせる職場
介護福祉士などの介護資格を取得することで、その専門性を活用し役立てることができる職種は多くあります。
在宅の職場はホームヘルパーが多く、施設の職場はケアワーカーが多く働いていますが、されぞれ介護業務に従事している職員の呼び方には、次のようにいろいろな名称があります。
ケアワーカーとは
ケアワーカーは、介護を必要とする高齢者などの介護に携わっている方の総称として呼ばれているのが一般的で、通称みたいなものですが、介護職員が正式な職種名です。
特に高齢者や障害者の入所施設に従事している介護福祉士などの介護職員をケアワーカーというケースが多く、一般の介護や介助を行っている方でもケアワーカーと呼ばれていることがあります。
ホームヘルパーとは
在宅介護に従事している職員をホームヘルパーと呼ぶ場合がほとんどで、ケアワーカーということはまずありません。
介護保険上の介護給付や予防給付での居宅サービスに従事する訪問介護員と同じ意味です。
ホームヘルパーの所属先には、在宅介護支援センター、居宅サービス事業所、ヘルパーステーションなどがあり、ホームヘルパーは介護職員全体でも多くの比率を占め、登録型や非常勤の勤務形態で働いている方が多い職場です。
生活支援員、生活相談員、生活指導員とは
生活支援員は、高齢者や障害者が入所している身体障害者施設や知的障害者施設に多く従事している職種になります。
生活相談員は特別養護老人ホームなどの介護老人福祉施設に従事し、生活指導員は保護施設などに従事している職種になります。