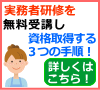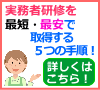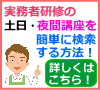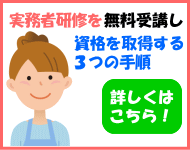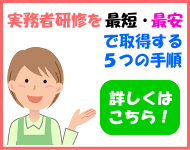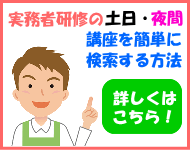介護福祉士の資格取得を目指して実務者研修を受講する場合には、既に取得している介護資格の種類に関わらず、医療的ケアの研修課程は必須科目になります。
ここでは、医療的ケアの喀痰吸引の研修内容について詳しく解説しています。
痰吸引が必要となる疾患や病状
ホコリや細菌が気管に付着し粘膜でくるまれ粘々とした黄色い固まりとなったものが痰といわれるものですが、身体が健康な人であれば、通常、痰が溜まれば咳をすることで体外に排出されるようなしくみになっています。
但し、次のような方の場合、自力で咳をし痰を排出できないので、その際には看護師や介護士が吸引処置を行います。
下記の呼吸器系疾患、筋疾患、神経変性疾患、脳機能障害などの病態が原因で嚥下機能や呼吸機能が正常に働かない方に対しては痰吸引を行う必要があります。
- 気管支喘息
- 慢性閉塞性肺疾患
- 筋ジストロフィー
- 筋委縮性側索硬化症
- パーキンソン病
- 脳障害
- 脳梗塞
- 脳性麻痺
また、筋力が衰え咳をするのが困難になったり、嚥下障害になったりする方の場合も、痰を吐き出せなくなり、気道に痰が絡みつき正常な呼吸が出来なくなってしまうので、痰吸引を行う必要があります。
呼吸を正常に保つ為、気管カニューレを行っている場合は、気管支や気管カニューレ、肺に痰が溜まったりすることがあり、それが原因で肺炎を発症したり、呼吸に支障が発生し最悪の場合は窒息したりすることもあります。
このような人命にかかわる最悪の事態を防ぐため、自分で咳をしたり痰を吐き出したり出来ない方には、痰吸引を適宜行うことが必要になります。
痰の吸引の種類・方法・留意点
介護職員が痰吸引を行える範囲
看護師などの医療従事者は、気管や咽頭からの痰吸引を行えますが、介護職員の場合は、次の範囲に限って痰吸引を行うことができます。
- 因頭の手前までの口腔内
- 鼻腔内
- サイドチューブ内を含んだ気管カニューレ内
喀痰吸引の種類と留意点
痰の吸引を行うタイミングは、定期的に行なうのは当然ですが、利用者の体調などにより痰が溜まる状況も変化しますので、利用者から要求があった場合や介護者が気づいた場合も都度痰吸引を行います。
また、利用者の中には、声を出して痰が溜まっていることを伝達できない方も少なくありません。
なので、介護職員は利用者がどんな表情や態度をとった場合に痰吸引をすべきか、担当の看護師や家族などにあらかじめ確認しておくことも大切です。
口腔内痰吸引
吸引カテーテルを□から挿入し、嚥下障害がある方に実施します。
鼻腔内痰吸引
吸引カテーテルを鼻腔から挿入し、咽頭部手前に溜まった痰を除去します。
※咽頭部手前に溜まった痰は、□腔内吸引では完全に除去することはできません。
気管カニューレ内痰吸引
気管を切開し、気管カニューレで呼吸を確保している方には、吸引カテーテルをカニューレ内に挿入し、痰を吸引除去します。
医療的ケア 喀痰吸引の管理人の受講体験談
実務者研修課程の受講科目で医療的ケアは必須科目となっており、講義50時間以外に実技演習も受講する必要があります。
医療的ケアの実技演習では、喀痰吸引と経管栄養、救急蘇生法の実技演習が行われます。
私も以前受講しましたが、かなりの時間を割いて練習した記憶があります。
最初は練習をしますが、手技だけでなく、模擬で利用者への声掛けのセリフもかなりあります。
ですから、おそらくどこのスクールでも実技演習の手順と内容、声掛けのセリフなどを記載した台本のようなものを配布していると思います。
まずは、その資料を何回も読んで手技を覚え、次に声掛けや報告内容のセリフを覚える必要があります。
実際のところ学校の練習だけでは、完全には覚えることができなかったので通学途中や自宅ではイメージトレーニングもやりました。
喀痰吸引の理解度テストは、本番で15分間ほどだったと思いますが、さすがに試験官役の講師の前では緊張しました。
実技演習の手技の基本的内容はどのスクールでも同じですが、声掛けや報告の仕方、手技の手順などは、個々のスクールにより若干の違いがあります。
また厚生労働省の研修規定では、口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引については、最低各5回以上の演習を実施することとなっています。
このカテゴリでは、実技演習動画も紹介していますので、この動画を見ておくと、およそどのようなことを学ぶのかが理解できると思いますので、参考にして下さいね!