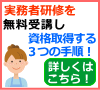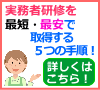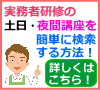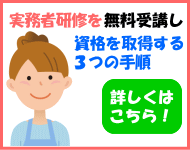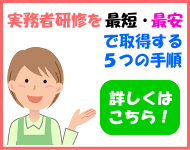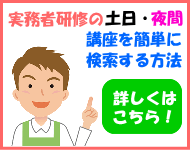介護現場では、人のマネジメントの進め方次第で良くも悪くもなります。
特に現場の最前線で活躍している介護ヘルパーの人事管理は、サービス提供責任者などの管理者にとっては重要なマネジメント要素となります。
次に、人事管理についてマネジメントの要素ごとに分割しサービス提供責任者などの管理者として行う仕事内容をみていきましょう。
訪問介護サービス業界の専門用語でもあるサービス提供責任者という言葉ですが、一般的には介護職員実務者研修や旧資格になりますが1級ホームヘルパーになれば担える法的に定められた正式な職種になります。
サービス提供責任者の役割は、現場の介護ヘルパーを統括マネジメントし、利用者に対して円滑に訪問介護サービスを提供していけるようにする立場にあります。
人を相手にするサービス業では、「サービスは人なり」ということわざもあるくらいで、特に介護サービスの仕事においては、人に関する要素は重要な比重を占めています。
極論を言えば、全職員の人質が高ければ、100%顧客満足度は向上し、介護事業における収益も伸びてさらに発展していくことにつながります。
人の質をいかに高めるか、質の高い人材をいかに採用できるかは、サービス提供責任者の手腕に大きく関わってきます。
しかし、実際は本人が持っている潜在的な能力や現状のスキルだけに頼ることは危険です。
なので、募集から職場配置まで、マネジメントという観点で職員の能力やマンパワーを管理しコントロールすることが必要になります。
通常、人事管理のマネジメントの流れには、次のようなプロセスがあります。
- 採用要員計画
- 試験・面接
- 採用
- 新人教育
- スキルアップ研修
- 職場配属
- 訪問シフト管理
- 業務評価と処遇
その他にも、労働基準法に遵守した就業管理、労働安全衛生法に基いた安全衛生管理、法律に基づいた給与計算、社会保険や福利厚生などの施設内規則についても整備することが求められます。
その他については、訪問介護事業の経営者が責任を持って担う業務ですが、サービス提供責任者(介護職員実務者研修・旧1級ホームヘルパー)の立場にある場合は、いかに経営的にプラス効果をもたらすことができるか、人質を高めることができるか、最適最良な介護サービスが提供できるかについて、模索し努力する姿勢が必要です。
人材を上手く活用するためには、各介護職員の持っている技能や能力、携わる仕事内容、業務対する評価、実績見合った処遇という内容が繋がり一連の流れ・サイクルとして回ってマネジメントされ、利用者が求めるニーズと合致した介護サービスが提供されることが重要です。
現在、少子高齢化社会真っ只中の日本では、65歳以上の高齢者が全国民の25%を越え、その内400万人が要介護認定者となり、2025年にはさらに200万人増加して600万人になると推定されています。
このような社会環境の変化により、利用者のニーズも多様化しているだけでなく、様々な介護レベルや難易度が要求されています。
なので、このような多用なニーズにしっかり対応できるスキルを持った介護ヘルパーに仕事を任せて、それぞれの要求レベルに合った業務を行った場合は、その実績に見合った評価を行い、十分な処遇を行なうことが重要です。
その結果、介護ヘルパー自身のヤル気や士気が高まり、介護技術のスキルアップに努めさらにハイレベルの仕事が出来るように努力するという好循環が生まれてきます。
このような状況をサービス提供責任者など管理者にある立場の者が、介護ヘルパーの稼働管理を通じて達成できるかどうかが、人質管理におけるマネジメントの要となります。
人事制度においても今では年功序列を採用している日本企業も少なくなってきましたが、最近では従業員の技能・スキル・力量・実績に応じて支給賃金を決定する「能力評価による人事制度」を導入する企業が多く一般的になってきました。
また、職員の業務実績と連動させた評価制度や給与体系の見直しを行う社会福祉法人も多くなってきています。
今後、介護業界でも個人の技量や実績に見合った評価を行い、ヤル気を引き出し能力をさらに高めていけるような人事制度を導入することが必要になってくるでしょう。