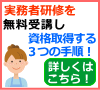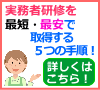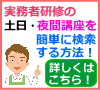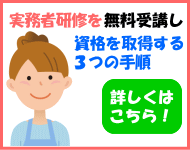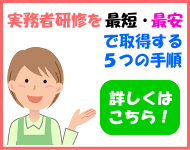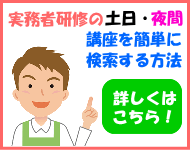介護給付と予防給付の2つに介護保険の給付は大別されます。
また、市町村特別給付という市町村の独自の給付を設けている保険者もあります。
介護給付は要介護者が利用でき、予防給付は要支援者が利用することが可能です。
介護給付・予防給付では、区分支給限度基準額が設定されており、これは居宅サービスの保険給付範囲や金額について、要介護認定などの認定結果に応じて上限額が月別に設定されています。
目 次
1-2.市町村が指定する介護給付サービス
2-1.訪問制介護給付の種類
2-2.通所・入所制介護給付の種類
3.介護給付(施設サービス・地域密着型サービス)の種類と概要
4-1.予防給付
4-2.予防給付と介護給付の相違点
4-3.市町村特別給付
1.各自治体による介護事業者および介護施設の指定
1-1.都道府県・政令指定都市が指定する介護給付サービス
| 給付種類 | 都道府県・政令指定都市が指定 | 利用者 |
| 介護給付 |
○居宅サービス
|
要介護者 |
| ○居宅介護支援 | ||
○施設サービス
|
||
| 予防給付 |
○介護予防サービス
|
要支援者 |
1-2.市町村が指定する介護給付サービス
| 給付種類 | 市町村が指定 | 利用者 |
| 介護給付 |
○地域密着型サービス
|
要介護者 |
| 予防給付 |
○地域密着型介護予防サービス
|
要支援者 |
| ○介護予防支援 |
2.介護給付(居宅サービス)の種類と概要
介護給付(居宅サービス)の種類とその仕事内容とサービスの概要について解説しています。
2-1.訪問制介護給付の種類
| 給付の種類 | 概要 |
| 訪問介護 | 利用者の自宅に訪問介護員(ホームヘルパー)や介護福祉士が訪問して行う介護サービスです。 具体的には、生活援助(掃除・洗濯・調理などの家事の援助)・身体介護(排泄・食事・更衣・入浴など)・通院などのための乗車降車の介助(訪問介護員の運転する車両で通院などを行う際の乗降と移動の介助・受診手続き)があります。 |
| 訪問入浴介護 | 入浴が困難な利用者宅へ専用の簡易浴槽を積んだ車両などで訪問し、自宅に浴槽を持ち込んで入浴サービスを行います。 |
| 訪問看護 | 医師の指示の基、自宅へ看護師などが訪問し、病状の観察、診療の補助(医療処置やバイタルサイン測定など)、療養土の世話(清潔保持や排泄の支援など)などを行います。 |
| 訪問リハビリテーション | 医師の指示の基、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が自宅へ訪問し、言語や嚥下などに関する機能訓練、家事等のIADL(手段的日常生活動作)、ADL(日常生活動作)や基本動作などを行います。 |
| 居宅療養管理指導 | 医療専門職である医師や薬剤師などが自宅へ訪問し、医学的観点からの療養土の指導・助言(栄養・口腔ケアなどの指導、生活上の助言や服薬を行うことで在宅生活を送る支援)を行うものです。 |
2-2.通所・入所制介護給付の種類
| 給付の種類 | 概要 |
| 通所介護 (デイサービス) |
日中の時間帯に入浴や食事、介護や機能訓練を、日帰り施設などで行う通所サービスで、自宅と施設の送迎もほとんどの場合実施されています。 介護者の介護負担の軽減、社会的孤立感の解消、生活の活性化などを目的としたものです。 |
| 通所リハビリテーション | 心身機能の維持・回復を主目的としたリハビリテーションの必要性が高い人に対応する通所サービスで、ほとんどの場合、通所介護と同様に送迎が実施されています。 また、食事や入浴介助を実施している介護事業者もあります。 |
| 短期入所生活介護 (ショートステイ) |
食事・排泄・入浴などの介護や日常生活上の世話、機能訓練を行うのが目的で、特別養護老人ホーム、老人短期入所施設などに短期間入所して行われます。 利用者本人の機能改善や活性化と共に、家族介護者の介護負担軽減や休養、急病や急用などにより一時的に介護をできなくなった場合にも活用されています。 |
| 短期入所療養介護 (ショートステイ) |
医療的依存度の高い場合やリハビリテーションの必要な利用者がいる場合に多く活用され、介護老人保健施設、老人性認知症疾患療養病棟、病院(療養病床)、診療所などで短期間入所して行われます。 |
| 特定施設入居者 生活介護 |
設備や人員配置などの一定の基準を満たす有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームなどでは、その施設に入所している高齢者の居室を自宅(居室)とみなし、施設職員が行う介護提供サービスを居宅サービスと同様とみなし、介護保険給付の対象とするものです。 |
2-3.福祉用具・居住関連の介護給付の種類
| 給付の種類 | 概要 |
| 福祉用具貸与 | 車いすやベッドなどの福祉用具が要介護状態で必要になる場合は、保険給付として貸与が受けられます。 |
| 特定福祉用具販売 | 入浴や排泄に関するような貸与になじまない福祉用具は、特定福祉用具としての購入費用を保険給付の対象としています。 |
| 住宅改修 | 要介護状態によって自宅改修工事は必要になった場合は、事前に保険者に申請手続きをとることにより、その改修費用の一部が保険給付となります。 |
| 居宅介護支援 | 介ケアマネジャー(護支援専門員)がケアプラン(居宅サービス計画)を作成する際、ケアマネジメントを行います。 |
3.介護給付(施設サービス・地域密着型サービス)の種類と概要
介護給付(施設サービス・地域密着型サービス)の種類とその仕事内容とサービスの概要について解説しています。
3-1.介護給付(施設サービス)の種類と概要
| 給付の種類 | 概要 |
| 介護老人福祉施設 | 介護を中心とした長期入所の生活施設で、食事・排泄・入浴などの介護・日常生活の世話、機能訓練や健康管理のサービスが提供される施設で、介護保険法による指定を受けた老人福祉法に基づいて設置される特別養護老人ホームが運営を行います。 |
| 介護老人保健施設 | 主に身体機能の維持期のリハビリテーションを提供する点に特徴があり、必要な医療、看護・医学的管理下での介護、機能訓練などが提供される入所施設で、設置許可を介護保険法に基づいて受けることで運営を行うことができます。 |
3-2.介護給付(地域密着型サービス)の種類と概要
| 給付の種類 | 概要 |
| 随時対応・定期巡回型訪問介護看護 | 訪問サービスの一種で特徴は、看護と介護の両サービスを提供、昼間・夜間を問わない24時間対応、利用者からの連絡により随時訪問も可能で、事前に予定計画された定期的訪問以外でも対応するというサービスです。 |
| 夜間対応型訪問介護 | 文字通り、訪問介護を夜間の時間帯に受けることができるサービスで、原則22時から6時の時間帯を含みサービス提供を受ける必要があり、昼間のサービス提供もこれに合わせて実施されます。 |
| 認知症対応型通所介護 | 1日の利用定員を少人数に限定して認知症高齢者の特性に配慮し、運営を行う認知症の利用者を対象とした通所介護のサービスです。 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 地域住民との交流や家庭的環境のもとで、利用者に合わせて訪問・通所・短期入所の三つのサービスを適宜組み合わせ、利用の入居者数を25人以内に限定し、在宅生活の支援を行うものです。 |
| 認知症対応型共同生活介護 (認知症高齢者グループホーム) |
地域住民との交流を図ることができるよう、住宅地に設置されることが基本とされ、5人以上9人以下を1単位として2単位までを定員とした共同生活住居において、認知症高齢者のために必要な介護サービスを提供するものです。 |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 定員が29人以下の特定施設入居者生活介護の事業者のことです。 |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 定員が29人以下の介護老人福祉施設のことです。 |
| 複合型サービス | 看護サービスなどを利用者に提供可能とすることで、医療的な問題にもある程度対応できるようにするために、訪問看護の事業を小規模多機能型居宅介護などに一体化させたものです。 |
4.予防給付と市町村特別給付の種類と概要
予防給付と市町村特別給付の種類とその仕事内容とサービスの概要について解説しています。
4-1.予防給付
予防給付と介護給付のサービスの種類はほとんど同じですが、相違点には次のような項目が挙げられます。
4-2.予防給付と介護給付の相違点
- 地域密着型サービスのうち、次のサービスに相当するサービスは設定対象外となる。
- 夜間対応型訪問介護、
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 複合型サービス
- 施設サービスは設定対象外となる。
- 要支援者のケアマネジメントは、地域包括支援センターで実施され、ケアマネジメントのサービスは介護予防支援となる。
- 介護予防という名称がサービス名の頭に記載される。
予防給付に関する介護サービスの提供や利用に際しては、「要介護状態に進行することを予防するための給付である」という認識が強く、介護予防を行うための効果的支援方法に関する基準が、法令上加筆されています。
4-3.市町村特別給付
介護保険法で定められた介護給付と予防給付以外に、市町村特別給付という市町村独白の給付内容を条例で規定することも可能です。
市町村により異なりますが、配食サービス、移送サービス、紙おむつの支給、寝具乾燥サービスなどを給付対象に設定しているところも実際にあります。